読み物「密約」検証結果外伝 若泉 敬─知られざる「密使」の苦悩
「密約」 公表の2年後に自決
長男に 明かしていた舞台裏
「個人的には、核の再持ち込みこそ密約だと思う」。岡田克也外相は3月9日、1972年の沖縄返還をめぐる「密約」を認め、有識者委員会も「密使」の存在に初めて光を当てた。96年に命を絶った国際政治学者の若泉敬。その長男が初めて口を開き、友人からの書簡も明らかになった。「沖縄に殉じた男」の足跡と心中に迫る。
本誌 諸永裕司
(編集者注・週刊朝日に掲載された傑作ノンフィクションです。ぜひ「魚の目」の読者にもよんでいただきたいと思ったので、週刊朝日の了承を得て再録します)
その報告書の末尾には、次のような一文があった。
〈若泉─キッシンジャー・ルートが開かれたことは大いに評価できる〉
岡田克也外相から密約の検証を委嘱された有識者委員会(座長=北岡伸一・東大大学院教授)は9日、日米関係にからむ四つの密約についての報告書を出した。
そのひとつ、1972年の沖縄返還にともなう「核の再持ち込み密約」について、
「必ずしも密約とは言えない」
と結論づけながら、この交渉に人生を捧げた「密使」の存在を初めて認めた。 若泉敬(享年66)。
若泉敬(享年66)。
表の顔は京都産業大教授。
裏の顔は、沖縄返還交渉における佐藤栄作首相の「密使」。核の再持ち込み密約のシナリオライターだった。
戦後、米軍の施政権下にあった沖縄の返還にあたって、日本側は米軍基地に貯蔵されていた「核の撤去」を求めた。
一方、アメリカ側は、返還後も基地を自由に使用することのほかに、「緊急時の核の再持ち込みと通過の権利」を求めた。
若泉は、米側の交渉相手である米大統領補佐官のキッシンジャーとの壮絶な交渉の末、次の文言を盛り込むことで合意した。
〈日本国政府は、大統領が述べた前記の重大な緊急事態が生じた際における米国政府の必要を理解して、かかる事前協議が行なわれた場合には、遅滞なくそれらの必要をみたすであろう〉
アメリカは「遅滞なく必要をみたす」との言質をとることで、有事に核を持ち込める。日本は事前協議が行われなければ、「核兵器の持ち込みはない」と言い逃れできるというわけだ。
そのうえで、ふたりの「密使」は次のようなシナリオを描いた。
1969年11月の日米首脳会談の最後に、ニクソン大統領が佐藤首相に、大統領執務室に隣接する小部屋で美術品を鑑賞することを提案する。通訳も除いて2人だけで小部屋に入り、核の再持ち込みに関する秘密の合意議事録に署名、それぞれ1通ずつ保管する ──
予定では頭文字を記すだけのはずだったが、ニクソンがフルネームで署名をしたため、佐藤もこれに倣ったという。
 こうした交渉の経緯を、若泉は94年、『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』によって明らかにした。628㌻に及ぶ大著だった。
こうした交渉の経緯を、若泉は94年、『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』によって明らかにした。628㌻に及ぶ大著だった。
「一つの間違いも許されない」
出版前、若泉が何度となく口にしていた言葉を、早稲田大大学院教授の後藤乾一(66)は覚えている。じつは、若泉から命じられて秘かに執筆を手伝っていた。今年1月に出版した『「沖縄核密約」を背負って──若泉敬の生涯』で明かした。
「『細部まで徹底的に考証してほしい』と言われました。これは『危険な書』だとも」
国家の秘密を暴くだけに、「国賊」と呼ばれるかもしれない。襲撃されることも覚悟していたという。そのため、出版の前には、福井県鯖江市の自宅の塀をさらに1㍍ほど高くする工事を済ませていた。
「冒頭に『何事も隠さず/付け加えず/偽りを述べない』とわざわざ書き記したように、歴史の証言台に立つ思いだったのでしょう。国会に証人として喚問されることを想定していらっしゃいました」
後藤はそう回想する。実際、想定問答を繰り返す姿も目撃した。しかし、国は事実上、黙殺した。
この密約については当時、両首脳のほか、シナリオを描いた若泉とキッシンジャーの4人しか知らなかった。秘密合意議事録のその後について、若泉は『他策──』で次のようにつづっている。
〈「ところで総理、“小部屋の紙”(日米秘密合意議事録)のことですが、あの取り扱いだけはくれぐれも注意して下さい」
と、総理の眼をぐっと見つめる私に、
「うん。君、あれはちゃんと処置したよ」
と、総理は心なしか表情を弛めて言った。
“安心してくれ”といわんばかりの響きがあった。
それは具体的にどういう意味なのか、と一瞬訝しく思ったが、それ以上深追いはしなかった〉
処置した──
佐藤栄作首相がそう話した文書はしかし、自宅に残されていた。首相退任後に持ち帰った執務机のなかにあったことを昨年暮れ、首相の次男で元通産相の信二(78)が明らかにした。文書は、
〈1969年11月21日発表のニクソン米大統領と日本の佐藤首相による共同声明に関する合意議事録〉
と題され、69年11月19日付で両首脳のフルネームの署名もあった。
合意議事録の文書が存在し、若泉が残した記述も、その後公開された複数の米公文書と重なる。
しかし、岡田外相の命を受けて調査にあたった有識者委員会は外務省と同じく、密約とは認めなかった。
「先生が心血を注いで結んだ合意、命をかけて明かした歴史の真実が評価されなかった。あれが密約でなければ何だと言うのでしょう」
後藤は、『他策──』刊行から16年後の政府の公式見解に、若泉の無念を思う。
密約調査の結果発表を見守っていたのは、後藤ばかりではない。
これまで、メディアの取材を一切、拒んできた若泉の長男、聡一郎(50)が口を開いた。
「あの密約が日本にとって、沖縄にとってよかったのか、私にはわかりません。結果的に沖縄への負担が増したのだとすれば、息子として胸を張って人前に出ることはできないと思ってきました」
とはいえ、密約が認められなかったことには釈然としない。報告書が、
〈この(若泉─キッシンジャー)ルートを通してニクソン大統領の意向が佐藤首相に届いたことの意義は大きい〉
としているだけに、なおさらだ。
「国が、父の果たした役割を評価しながら、その結晶とも言うべき密約を認めない、というのは理解できません。残念です。父は決して嘘をつく人ではありませんでしたから。密使として動いたあの2年間は、父の人生にとってすべて、といえるほどのものでした」
若泉はいかにして密命を帯びることになったのか。『他策──』のなかに、こう記されている。
〈福田(赳夫・自民党)幹事長は、開口一番、引き締まった表情で、
「先生を全面的に信頼しての話ですが、沖縄問題の件でひと肌ぬいでもらえないだろうか。(略)アメリカ最高首脳部の意向を打診してきてもらいたいんです」
と単刀直入に要請してきた。(略)
「総理からぜひともお願いしたい、ということで、総理の意を受けて言っているのです」〉
前年には米国防長官マクナマラとの単独会見記を「中央公論」に発表するなど、米ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究所(SAIS)への留学時代に培った人脈を見込まれたのだ。37歳の国際政治学者は、密使の打診を断らなかった。
〈この一九六七年九月二十九日で、私の第一の人生は終り、第二の人生が始まったようなものであった〉
家族や同僚などにも察知されてはいけない。孤独な闘いが始まった。
聡一郎はこのとき、7歳。
父はめったに家にいなかった。印象に残っているのは、電話をしている父の姿だ。
「いつも電話ばかりしているので、弁護士の母が『仕事にならない』とこぼしてました。夕食でも、食卓まで黒電話を引いていました」
残された請求書では、国際電話料金が69年当時、34万円を超える月もあった。そのすべてを若泉は自腹でまかなっていた。
海外出張でもよく家を空けた。帰らない日が続き、母ひなをは一時期、本気で浮気を疑ったという。
沖縄返還から3年後の75年夏、聡一郎は留学中の父からアメリカへ来るように言われた。
「会わせたい人がいる。沖縄返還交渉のとき、お世話になったんだ」
このとき、父が「密使」だったことを初めて知った。15歳の聡一郎が、元大統領補佐官のロストウを訪ねると、テキサス大の研究室には額が飾ってあった。
「危機」
筆で書かれた二文字は、父が書いて贈ったものだった。
80年、父は突然、「東京を離れる」と言いだした。京都産業大教授の職を辞し、故郷の福井県鯖江市へ居を移すという。50歳での隠遁には、弁護士として家計を支える母も反対した。でも、言いだしたらきかない。
聡一郎は居間に呼ばれ、ふたりきりで向き合った。転居するのは、沖縄返還交渉について執筆するためだ、と父は打ち明けた。
「本を書けば、俺は国賊になる。お前の人生も吹っ飛んでしまうかもしれない。でも、わかってほしい」
聡一郎は言葉が見つからない。また、家庭の平穏が遠ざかる。いや、二度と訪れないかもしれない。でも、反対しても無駄なことはわかっている。黙って聞くしかなかった。
受験を控えた聡一郎を残し、父は母と次男の核を連れて鯖江に帰った。まもなく、執筆用に離れも建てた。
会いに行くと、庭に面した16畳ほどの和室は資料で足の踏み場もない。文机に線香を1本立てて、父は原稿用紙に向かっていた。
5年後、母が急逝する。弁護士として福井と東京を往復する激務が体を蝕んだように、聡一郎には思えた。まだ55歳だった。
火葬場で納棺した後、父は火を入れるためのスイッチを前に固まっていた。
「代わりに押してくれないか」
それでは後悔することになるのではないか。聡一郎は初めて、父に異を唱えた。
「やっぱり、父さんが押したほうがいい」
まもなく、父は観念したかのようにスイッチに手をかけた。その右手は震えていた。
それから、父は酒に逃げた。一晩で一升をあけることもあった。厳格で武士を思わせる父が崩れる姿を初めて見た。
「一緒にいてくれ。会社なんて、一日ぐらい休んでもいいだろう」
週末ごとに鯖江へ呼び戻された。
それから9年。
94年5月、聡一郎のもとに小包が届いた。
「ああ、来るべきときが来た」
直感どおり、なかには分厚い本が入っていた。
『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』
題名は、日清戦争時の外相、陸奥宗光がその著作『蹇蹇録』の結びに記した言葉から取っていた。
ベトナム戦争のただなかで、基地の自由使用を求めるアメリカから外交のテーブル越しに沖縄の施政権を取り戻すには、核の再持ち込み密約を結ばざるをえなかった──
そこに、「密使」としての父の苦悩が読み取れた。日米の首脳が密約に署名してから25年。戦後50年を迎える前年のことだった。
出版の直前、若泉は交渉相手だったキッシンジャーに連絡する。
「私は評論家ではないので、書く以上は真実を書く。あなたのような伝記は書かない」
キッシンジャーの回想録『キッシンジャー秘録』では、「小部屋」で作成された合意議事録についてはまったく触れられていなかった。
聡一郎は父のキッシンジャー評を聞いたことがある。
「海千山千で、本音なんて言う奴じゃないんだ」
交渉では、「本当のことを言え」と父が迫ったこともあったという。
しかし、覚悟の出版にもかかわらず、世間の反応は冷ややかだった。
羽田孜首相(当時)は、
「核密約はありません」
とのコメントで一蹴した。
日米安保条約にかかわる秘密が暴かれたというのに、若泉が望んだ証人喚問はおろか、国会でもほとんど審議されない。
メディアの反応も鈍かった。政治問題としてではなく、とりあげたのはいずれも書評欄だった。94年7月3日付の朝日新聞で、東大教授の山内昌之はこう書いた。
〈行動派の学者とはいえ社会科学者がかくも最重要の国家の政策決定に秘密裡に関わり、その機密をいま公開した是非は、今後も朝野の議論を賑わすであろう〉
しかし、その予想ははずれた。
目先のカネに狂乱したバブル経済の崩壊を目の当たりにしながら、国の根幹にかかわる安全保障の問題を顧みようともしない社会を、若泉は「愚者の楽園」と呼んだ。深い失意に沈み、世間ともいっそう距離をとるようになった。
とはいえ、親しい友人たちには著作についての感想を求めた。
〈先に謹呈した“拙著”(私なりに心魂を傾けました)に対い(ママ)する、大兄の率直な御高評を承わりたく、御芳翰を切々お待ちして居ります〉
そこには、相手を試すかのような趣さえ漂う。
学生時代からの友人で、鎌倉に住んでいた池田冨士夫は3度にわたって催促を受けた。その思いに応えるように返した読後感想文はじつに、便箋274枚に及ぶものだった。
若泉の晩年、秘書役を務めていた福井県商工会議所専務理事の鰐渕信一(62)は言う。
「先生からは、死後、書簡類などの一切を焼却するように言われていましたが、これを捨てることはとてもできませんでした」
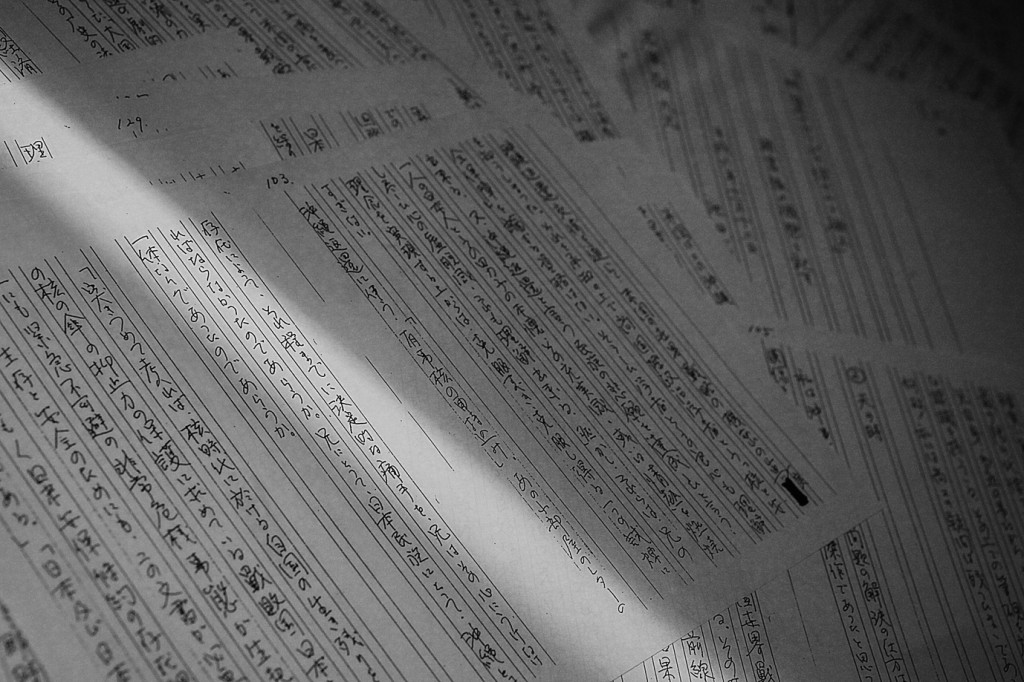
手元には、池田からの計8通の手紙が残された。
1通目となる読後感想文の冒頭には、こう記してある。
《若泉が私に真剣勝負を挑んでいる、そうした心を突き刺すような思いであった》
それだけに、真正面から向き合わなければと考えたのだろう。
若泉の人となりにも触れている。
《相手の目をじっと見る。瞬きもせず見続けると言う事は、それだけの心得がないと常人には難しい一つの業である》
《相手が誰であらうと、臆する所もなく、言うべき事を言う。「NO!」と言うべき時には、相手の意図に斟酌する事なく、断乎として「NO!」と自己の見解を主張する》
若き日々を振り返った後で、本題に入っていく。
《民族の悲願、達成に伴う日本の代償は(核の再持ち込み密約という)「小部屋のレター」唯一つであった》
戦争で奪われた領土を外交交渉によって取り戻した点を、
《歴史的な傑作》
と評価したうえで、こうつづる。
《兄のライフワーク“他策”は沖縄返還に伴う日米交渉の実態についての、歴史的原典として公刊の時をもって確定した、私はそう信じている》
一方で、池田は、引用の多さに辟易すると正直に記し、読後に抱いた違和感も伝えている。
《兄の書物は、力作である。その周到な準備と努力には心からの敬意を表している。然か(ママ)し、それはそれである、(略)私には兄の心情の実体を理解する事は出来そうにない》
それは、『他策──』の末尾に記された言葉についてのものだった。
〈私は筆硯を焼く〉
すべての文章、つまりは書物を捨てる、との覚悟である。
池田はその心中に思いを馳せる。
《沖縄返還交渉を通じて、米国の世界戦略の機密の真実を知ってしまった。それを承知の上で尚国際政治学者として「核と安全保障」を論ずる資格はない》
若泉は学者としての良心に苛まれているのだろうと理解を示しつつ、期待を捨てきれない。
《これからが兄の生涯の理念を実現する時ではないか。沖縄返還が実現したからと言って、日本の再独立が果された訳ではない。日本はまだまだ国際的な危機に直面している。兄の理念を実現する、その時代が来ている》
そのうえで、こう問いかける。
《五十才を期して都落ちを実践して、その後蟄居の十四年間、一冊の書物を著して、兄は自身のライフワークの完結と決している。一体、兄にとって「沖縄」とはなんであったのだらうか。沖縄返還交渉にたずさわった二年間の、その為だけが兄の人生のすべてゞあったのだらうか》
文面には哀切さえ漂う。
《何故兄一人が、そうも心に深か(ママ)い痛手を負い、一人筆硯を焼いて沖縄二十万の霊に殉じなければならなかったのであらうか》
若泉の思いつめたような文面が気にかかり、池田は福井県鯖江市の自宅を訪れている。読後感想文を送ってから1カ月ほどたった94年12月15日のことだ。
案内されたのは、若泉邸の前にある地下1階、地上2階建ての建物だった。薄暗がりの書庫は空だった。「筆硯を焼く」の言葉どおり、3万冊とも言われる蔵書はすでに処分されていた。
「書物はすべて焼いた。蔵書は学者の命なんだ」
国際政治学者として死んだことを伝えると、若泉は紙を見せた。そこには、こう書かれていた。
〈この世を去るにあたって〉
(文中敬称略、以下次号)









 現代プレミアブログ
現代プレミアブログ