わき道をゆく
- わき道をゆく
- 第222回 現代語訳・保古飛呂比 その㊻
(文久三年)七月 一 七月二十日、太守さまが三ノ丸で諸士に言い渡された御意の内容 去年以来、公武の関係が穏やかでないため、我らは弱年の身をもって朝命(天子の命令)を受け、勅使に従って東下西上(京都から江戸に下り、さらに江 […]
- わき道をゆく
- 第221回 現代語訳・保古飛呂比 その㊺
[参考] 一 (文久三年)六月二十四日、藩にて次の通り。 口上覚え このたび長州において兵端が開いた件につき、応援して(敵を)打ち払うよう京都より御沙汰があったが、彼(相手国側)は拒絶の命があったことをまだ知らない。そう […]
- わき道をゆく
- 第220回 現代語訳・保古飛呂比 その㊹
一 (文久三年)四月五日、初夜(現在の午後八時から九時ごろ)ごろ、(義弟の)本山誠作殿から使いが来て、こう言った。「(誠作の長男の)貫之助が先ほど、小高坂村西町に住む徒士(=かち。土佐藩の下士身分。郷士の下で、足軽の上に […]









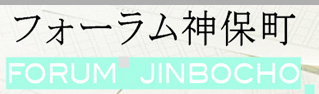



 現代プレミアブログ
現代プレミアブログ